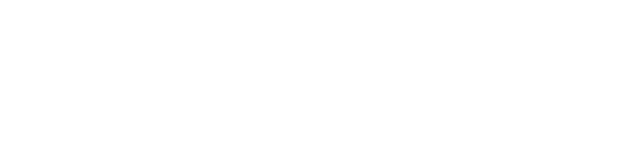並み居る外産馬の中で健闘するこの人馬の姿に感動を覚え、そして勇気づけられた人も決して少なくないことと思います。ここではこの人馬に焦点を当てて、その軌跡をご紹介して行きたいと思います。
<序章>
大田芳栄は1984年、神奈川県に生まれる。
11才の時に世田谷の弦巻少年団で乗馬を始め、東京農業大学で馬術部に所属し、全日本学生馬術女子選手権優勝など輝かしい戦績を数多く残す。
卒業後は東京乗馬倶楽部でインストラクターとして社会人のプロの第一歩を踏み出し、2007年にパーチェ(佐藤正江氏所有)と出会う。
そして東京乗馬倶楽部で5年を過ごした後に独立し、神奈川県相模原市にスクアドラ・フェリーチェを設立。彼女は新しい環境でパーチェの調教を再開し、現在に至る。
<第1章>出会いから第4課目
パーチェとの出会いは2007年も押し迫った12月。彼女はパーチェの印象をこの様に語っています。
そして翌年には次の成績を残しています。
2008年 4月 3課目A 63.030%
9月 4課目 58.190%
こう書くと非常に順調に見えるかも知れませんが、その頃のパーチェはまだ5才。競技場での環境の中でのパーチェの反応は尋常ではなかった様で、彼女はその頃のパーチェをこの様に回想しています。

「最初はとにかく暴れまわっていたので、それを落ち着かせることが大変で、試合会場でも準備運動で暴れまわり、他の馬にも迷惑になるくらいでした。その暴れ方は半端ではなかったので、当初はそういう意味で有名になったような気がします。本当にロデオ状態でした。」
「この時期、基本的には調教などを大きく変更したことはないのですが、講習会や試合毎に少しずつ馬が成長していったように思います。分からなかったり、上手くいかず煮詰まってしまったときなどは基本的に北原さん(JRA馬事公苑 北原広之氏)に聞きに行っていましたね。あとは、他の方のトレーニングを見ながらヒントにしたり、アドバイスを取り入れながら進めていきました。」
この時期の課題
「パーチェに乗り始めた時、ハミにもたれかかる事(前のめりになる事)が解決しなければならない課題でした。特に駈歩がバランスを維持しづらかったです。そのため、まずは準備運動の時からあまり頭を低くせず、馬自身にバランスをとらせるように運動を進めました。
もたれかかって来た時には、馬に付き合って人の身体が前にいってしまうのではなく、多少馬とぶつかったとしても、もたれかかるバランスになってはいけない事を教えました。
もたれようとしてハミにぶつかる→手綱は許されず推進される→バランスが起きる→人馬共にコンタクトが楽になる、これは良い循環ですが、最初のうちは手綱が許されずに推進がかかることで苦しくなって立ち上がったり、走り出すこともありました。
とにかく繰り返し同じことを毎日要求し、こちらの要求しているバランスをパーチェに理解してもらいました。それは筋力的にもついて来なくては出来ないことですし、精神的にも受け入れてもらわなくてはならないことなので毎日行いました。
試合では、普段のトレーニングでバランスを確立できるようにしていたつもりでしたが、経路の後半になるとやはりバランスが前のめりになりやすく、反対駈歩が勢いで回ってしまったこともあります。
速歩は比較的早い段階でバランスを維持できるようになったので、前肢のさばきが良くなりました。これが伸長速歩でみせられるようになり、得点を得られました。」
「騎乗面以外でのこの時期の問題点としては、曳き馬もまともにできなかったことです。これは乗っているときに暴れることにも繋がっているのではないかと思い、雨の日などを利用して“曳き馬の練習”もしていました。最初は曳いていても走る、跳ねる、と振り回されていました。とにかく暴れなくなるまで、1時間くらい歩いたときもありました。これは長期にわたり続けました。」
「しかし、最初はとにかく暴れまわっていたパーチェも調教が進み、セントジョージくらいからは無駄に暴れることが減ってきました。」
では実際のその頃の運動を動画で見てみましょう。
動画1
動画2
馬場馬の新馬調教の一環としてコンビネーションジャンプを行ったものですが、こちらのアプローチも非常に丁寧で、一鞍の運動の中で馬に負担を与えることなくキッチリとその日の成果を挙げています。
ちなみに箱番を行っているのは当時東京乗馬に勤務していた林伸伍氏(現アイリッシュアラン所属)
(次回に続く)